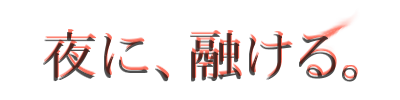
「小芝居ユニット/Funny Butterflies.」の
BLエチュード作品『夜に、融ける。』をノベライズ化いたしました。
『夜に、融ける。』は2013年の6月から7月にかけて彩の国某所のカラオケ店の片隅で開催された、
全4回のエチュード(即興芝居)であり、わたくし二山は記録係兼参加者として関わらせていただきました。
その後、「Funny Butterflies.」の
内容を整理し、シーンをつけ足した形でノベライズさせていただいております。
今回は特に指定のつくシーンはありませんが、BLの苦手な方はご注意ください。
また、昨年の夏に公開した『首吊りの夏』と世界観が繋がっておりますので、
もしご興味が出た方はそちらも楽しんでいただければ幸いです。
↓
↓
↓
夜に、融ける。[前篇]
|
あいつは夜店で売られている夏の金魚みたいな奴だった。すくおうとしてもひらりとすり抜けていく人を食ったような優雅さと、与えられた空間の中で自由に生きる奔放さを持った男。あいつに対してそんな印象を俺が持つのも宵町金魚(よいまち・きんぎょ)なんて冗談みたいな名前をあいつがしていたからかもしれない。そういう俺だって唄屋護郎(うたや・ごろう)なんてけったいな名前を授かっていたものだから、揶揄はそれほどしなかったが。俺はあいつを投げやりにキンと呼んで、あいつは俺を甘ったるい声でウタちゃんと呼んだ。家が近かったこともあり、俺たちは大して共通項もないまま一緒に育ってしまっていた。 盆の初日、夜も更けてから小皿に乗せた蝋燭とマッチを持って玄関を出る。とっくに寝静まっているらしいキンの家が少し離れたところに見え、その背後にある山の中腹で明かりがちらちらと輝いていた。おそらく明かりの道筋の先にある汀(みぎわ)神社の人々が、提灯を灯して回っているのだろう。 明後日、汀神社で夏祭りが開かれる。いつも盆の三日目に開かれ、ヨーヨー釣りだお面だ射的だと買ったところでガラクタにしかならないものを売る店と味の濃い食い物の店が並ぶだけの、凡庸な夏祭りである。 そうは言っても、この祭りにしかない屋台も紛れ込んでいるのはさすが田舎町と言うべきか。「赤笛」という人差し指と親指の間ほどの長さをした竹の笛に小さな鈴を入れ、その周囲を赤い糸でぐるぐる巻きにして房の形に結んで閉じこめたものがこの夏祭りでは売られているのだ。汀神社の言い伝えが絡んでいるらしく、俺が小学生の頃に、郷土を学ぶ授業だかなんだかでわざわざ神主が来て説明していた気もするのだが、どうにも寝ていたようでその由来を思い出せない。 俺は蝋燭を地面に置き、マッチを一本取り出して火を点けた。炎は一瞬大きく燃え上がり、それから平静を取り戻したかのように橙の色をたたえる。マッチから蝋燭の芯へそっと炎を移すと、そのまま天に繋がる糸になりそうな、細長い灯火が輝いた。つられるように上を見ると星が一つ落ちたような気がして、また視線を下へ戻すと蝋燭の炎は不思議と小虫を寄せ付けず、ただ穏やかに燃えていた。 盆の二日目のことだ。俺がサッカー部の練習を終えて校庭横の水道で頭から水をかぶっていると、 「ウタちゃん」 美術室の窓からキンが顔を出し、こちらに手を振っていた。俺は驚いて、思わず蛇口に頭をぶつけた。 「ごめん。びっくりするよね、急に声かけたら」 校舎の一階、人気のない美術室の窓に寄りかかって、うざったそうな前髪を気にもせずに笑いながら、失敗、とキンは言った。 「お前、なんで……」 「美術室、空いてたから?」 自分のことを俺に聞いてどうする、という問いはこいつには何の効果もない。それは幼なじみとして腹立たしいほど学習している。 「昨日さ」 「は?」 「迎え火、してたでしょ」 キンが窓枠に手をついて、話し込む姿勢になっている。俺はタオルで髪と顔を拭きながら、キンの方へ近づいた。 「ああ。……見てたのか」 美術室の窓は物置との兼ね合いで一階と二階の間とも言うべき位置の高さにあり、キンはどうやら見えないところで椅子を重ねてその上に立って顔を出しているようだった。危ないから止めろとさんざん注意しても、一向にキンは学習しない。少し、不公平を感じる。 「うん。なんかね、ぼーっとしてたら光が見えて。あったかいオレンジのやつ。きれいだなぁ、って思って」 「……そうか」 「でね、炎がゆらゆらってしたときに、ウタちゃんの影も一緒にゆらゆらって動いて、やっぱりきれいだったよ」 「小学生の日記文にしか聞こえないんだが」 俺は深く息を吐いて、キンのいる窓と向かい合うように座った。美術室の窓を見上げ、体育座りをしている俺の姿は端から見たらかなり奇妙な光景だろう。部活の連中は大方帰った後だったので、どうでもいいと言えばどうでもいい心配だが。 「だってオレ、言葉ってよくわかんないしー」 「およそ人類の台詞とは思えないな」 キンの語彙の少なさは、彼にとって言葉というものが生活する上で必要ないからこそのものだろう。 「絵だったら、なんとかなるのにね」 「そんな芸当ができるのは、お前だけだ」 キンは絵を描く。むしろ絵を描くこと以外何もできない。油絵が好きで、キャンバスに色をおき、広げ、また別の色を散らし、キンはキンの言語で感情を表す。下世話な話だが、キンの絵には値段がつく。聞いた話ではキンの親がネット上に我が子の絵を親バカのつもりでアップしたのが始まりで、それからあれよあれよと噂が広がり、本人がさっぱり意識していないまま、今では高校生ながら絵画の世界の新星と目されていた。俺にはよくわからない世界である。 「明日の夏祭り、ウタちゃん行く?」 「……さぁ、どうだろう。今のところは特に」 「来てよ」 無邪気にキンは言う。俺は返事をしようかどうか、少し迷った。するとキンは話題を変えた。 「なんかさぁ、これロミオとジュリエットみたいだよね」 「……は?」 「窓から見てる人と、下から見上げてる人の話なんでしょ、ロミジュリって」 「略すな。あとあれは悲恋の話だからな」 「ふぅん。でも勘違いで死んじゃうのってちょっと喜劇っぽいよね」 「知ってんじゃねぇか、内容」 からかったな、と俺は睨むが、キンはへちょっと笑うばかりだ。そして片手を上げて 「じゃ、夏祭りで待ってるね、ロミオ」 次の瞬間、キンは金魚のようにひらりと姿を消していた。夢だったのかと思うくらいに清々しい消えっぷりで、少し感動した。俺はそのまま立ち上がって砂埃を払い、家に帰った。 盆の三日目の晩、結局俺は夏祭りに足を運んでいた。山の麓から汀神社までの道のりに提灯が転々と吊り下がっており、普段は真っ暗闇に包まれる山道を照らし出している。時刻は八時半。地域の小中学生が祭りから帰路に着く流れに逆らうように汀神社を目指していると、 「あれ、ゴローじゃん!」 「こんばんは、唄屋くん。これからお祭り行くの?」 帰る人並みの中からやたら派手な風体の二人組に声をかけられた。 「ああ。勇次郎と片桐か。誰かと思った」 クラスメイトの上沼勇次郎と片桐美鶴が、りんご飴片手にこちらに近寄ってくる。しかもなぜか揃いの龍の絵が入った浴衣姿である。 「そうだよなぁ。提灯の明かりはあっても薄暗いし」 「上沼、たぶんそういうことじゃないと思うよ。僕らのこの格好があまりにも祭りに浮かれた人々風だから唄屋くんは戸惑ってるんだよ?」 「いや、そんなつもりは……」 そう言いながらも実際、勇次郎はともかくとして片桐がこうして浴衣まで着て祭りに顔を出しているのは意外だった。祭りの騒がしい雰囲気が苦手そうだし、よりによってクラス内でも不良ポジションに近い勇次郎と祭りを楽しむような行動に出るタイプだとは思ってもみなかった。と言うより、片桐が勇次郎に無理矢理連れ出されているように見える。 「やだなぁ、美鶴。確かにオレは浮かれている、浮かれているとも! だかしかし祭りとは浮かれてなんぼのもんじゃなかろうかと、そうご提案したい!」 「年中お祭り男は黙ってなよ」 やはり俺の推測は間違っていないようである。片桐の不機嫌バロメーターが目算だが80%前後で推移している。それに気づいていないのか、あるいは素知らぬ振りをしているのか、勇次郎が話を続ける。 「お前は? 一人で祭りって寂しくない?」 茶化すような口振りの後、勇次郎は少し目を見開いて、しまった、という顔をしていた。片桐は普段の穏やかな雰囲気を消して、 「上沼、言葉を選べ」 忠告と言うよりは叱咤に近い語気でそう言った。俺は決まりが悪くなって、曖昧に笑ってから話題を変えた。 「それにしても、珍しい取り合わせだな。勇次郎なんか、毎年女子と来てるイメージがあったのに」 その瞬間、かなりわかりやすい形で勇次郎と片桐はぎくっと肩を跳ねさせた。 「あー、いや。今年はその……たまたま、みたいな?」 「まぁ、あれだよ。美鶴の壮行会ってヤツ。 ……あだぁ!」 急に勇次郎が奇声を上げた、よく見ると下駄を履いた足の甲が赤くなっている。 「ちょ、素足踏むヤツがあるか!?」 「はーい、ここにいまーす」 なにかNGワードがあったらしい。片桐は右フックをかましつつ、ごめんね、よいお祭りを、と俺に言って逃げ出した勇次郎を追いかけていった。遠くの方で、 「攻撃を続行しないでくれくださいー! んじゃ、またな、ゴロー!」 勇次郎の声も聞こえた。そうしてぎゃあぎゃあと騒ぎながら二人はまた人並みに消えていった。 「……壮行会?」 片桐はどこかへ冒険にでも行くのだろうか。よくはわからないが、無事を祈っておこう。 〈後篇へ〉 |