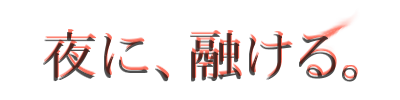
「小芝居ユニット/Funny Butterflies.」の
BLエチュード作品『夜に、融ける。』をノベライズ化いたしました。
今回ちゅーのシーンがあるので、BLの苦手な方はご注意ください。
↓
↓
↓
夜に、融ける。[後篇]
|
夏祭りの会場である汀神社に着くと、屋外だというのにソースが焦げた匂いとチョコレートの甘い匂いが混じり合った独特の空気が充満していた。 キンの姿はぱっと見る限り確認できなかったので、晩飯代わりに焼きそばを一パック買い、人混みの多い屋台を抜けようとする。と、例の赤笛が並べられている屋台が目に入った。赤というより朱色とでも呼んだ方が良さそうな色合いの笛が、屋台に一つだけ吊られている豆電球の光を受けている。店番の老人が俺をちらりと見て、呟くように言った。 「あんたは、買った方がいいと思うよ」 「……え?」 どういう意味か問う前に赤笛が俺の手に押しつけられる。「赤笛、一つ百円也」の看板を見て、まぁ百円なら、と俺は老人に硬貨を渡した。その背後で下駄がからんころんと大きな音で鳴ったので振り向くと、朱金色の鮮やかな浴衣を着たキンが、綿飴片手に通り過ぎていくところだった。キンは綿飴に夢中のようで、俺に気づかないまま、神社の本殿へと歩いていく。俺は人混みをかき分けて、その後を追った。 「キン! ……待て、キン!」 祭りの喧噪から抜け、静まり返った本殿の前でようやくキンはこちらに振り返った。 「あ、ウタちゃん。来てくれたんだ」 「お前が言ったんだろう。来いって」 「……オレが来てって言わなかったら、お祭り来なかった?」 俺は黙り込んだ。キンは続けた。 「オレが死んでから、ウタちゃんはあんまり笑わないね」 そう。一年前、キンは死んだ。キンの絵の才能を妬んだ男子生徒に殺された。 「……自覚はある」 「そっか。嬉しいけど、嬉しくないなぁ」 キンは食べ終わってしまった綿飴の棒を持て余しつつ本殿の階段に腰掛けた。俺もその隣に座る。 「どういうことか、そろそろ説明しろ」 「説明もなにも、ウタちゃんが迎えてくれたから、オレは来ただけだよ」 迎え火って何のためにやるのか、知ってるでしょ? とキンは愉快そうに言った。 「父さんと母さんはまだオレが死んだの、認められないから、迎え火してくれなかったし。まぁ、あんな死に方しちゃったしね」 一年前、キンが学校の美術室で絵を描いていると、ある男子生徒が訪ねてきた。そいつが顔見知りの美術部員だったので、キンはなんの疑問も持たずにそのまま作業を続けた。男子生徒は部屋にキンしかいないことを確認して、それから催涙スプレーを噴射し、身動きのできなくなったキンを椅子に縛り付け、ナイフで何度も刺した。そしてキンの血を絵の具にして、一心不乱に「作品」を描いているところを発見され、捕まった。今でも事件の裁判は続いている。 「……そんなに、軽く言えることなのか?」 「ウタちゃん?」 「お前の死は、そんなに軽い口調で済まされることなのか?」 今度はキンが黙り込む番だった。 「悪い。別に俺、お前にそんな顔させたくて言ったわけじゃない。ただお前が、宵町金魚がいなくなったことって、俺にとっては天変地異みたいな大事だったのに、お前にとっては、そうじゃなかったのか、って思って」 共通項がほとんどないような、一緒にいただけとしか言えないような、そんな関係だったけれど。 「俺とお前は、一緒にいなきゃ駄目なんだって思ってた」 ぼんやりしていて、いつも出遅れて、人を遠くから見るだけで満足してしまうようなキンがまともに生きていくためには、俺みたいなお節介野郎が必要なんだと本気で思っていた。その言葉に、キンは意外そうな顔をした。 「確かに、オレはそうかもしれないけど。でも、ウタちゃんはしっかりしてるし、オレがいなくても、きっと」 「じゃあ俺がこれから先、誰かと過ごすことになっても、お前はいいんだな」 「……その言い方は、ズルいなぁ」 弱々しくキンは笑った。 「いいわけないよ。……ずっとオレのこと、考えててほしい。けど、それじゃあウタちゃんがうまく生きられない気がする」 俺は頭をバリバリを引っかいて溜息を吐いた。 「どっちがズルいんだか」 「そう? ……ごめんね」 俯いたキンが俺の手元を見て、あ、と声を上げる。 「赤笛、買ったの?」 「ん、ああ。ほとんど押しつけられたようなもんだけど」 「あれ、じゃあ気づいてないの?」 「何に」 キンが急に立ち上がって、からんころん、と下駄を鳴らした。祭りの提灯が、キンの背後で踊っている。 「それは、さようならの笛、だよ」 ウタちゃん、あの授業忘れちゃったの? とキンは含みを持たせて言う。 「睡魔に負けて、覚えてないんだ」 「じゃあ、教えてあげるね。……むかーしむかし、」 キンは物語を紡ぎ始める。 「あるところに奥さんを早くに亡くした男がいました。男はとても哀しくて、奥さんを弔うために小さな竹の笛を作って演奏をしようと考えました。けれど、妻のいる冥土に果たして音色が届くのか、男は不安に思いました。そこで汀神社の神様に、どうすればいいか相談したのです。神様は言いました。貴方の血で染めた赤い糸を笛に巻き付けなさい。そうすれば、貴方と貴方の妻を繋ぐ赤い糸となり、ほんの少しの間、生者と死者の国を重ね合わせてくれるでしょう、と。男はお告げに従って、赤笛を作り、送り火の日に演奏しました。すると、微かに男の妻の声がしたのです」 一度言葉を切って、キンは俺をまっすぐに見つめた。 「”ありがとう。もう、十分でございます。どうか、どうか哀しみだけを見つめないでください。貴方の笑顔が、私の幸せであることを忘れないでください。どうぞ、お元気で。……さようなら”」 「……キン!」 俺はとっさに立ち上がってキンの腕を掴もうとした。けれど、その手はあっさりすり抜けた。俺はバランスを崩して、石畳に膝をつく。 「ねぇ、ウタちゃん」 「……っ」 すぐ傍に、しゃがんだキンの顔があった。眠そうなたれ目に、薄い唇、うざったい前髪。一年前まで見慣れていた顔が、今では遠く感じる。 「オレ、本当は聞き分け全然良くないんだよ」 茶色がかった瞳が、揺れている。 「赤笛のお話みたいに、ちゃんとさよならなんて言いたくない。さよなら、したくない。ウタちゃんの隣に、いたい」 今までずっと、何があってもしょーがないか、の一言で済ませていたキンが、ぼろぼろとこどものように涙をこぼしていた。きっと、無理なことなんだろうと思いながらも、俺はキンの耳元に囁いた。 「……いればいいだろ、いくらでも」 そして、触れる感覚のないキスをした。 しばらくして、ようやくキンが目と鼻を真っ赤にしながらも泣きやみ、落ち着いてきた。 「あーあ。オレ、本当にウタちゃんに取り憑こうかなぁ」 「だからそうしろって言っただろ」 「聞き分けがないところは似てるんだね、オレたち」 鼻をすんすん言わせながら、キンが目をこすった。どうとでも言ってくれ、と俺は投げやりに言って、それから尋ねる。 「俺がお前のとこ行くのは、なしなのか」 「なし」 キンと会話をしてきて、これほど早いレスポンスがあっただろうか。 「なーし。なし。絶対なし」 「わ、わかった、わかったから。また泣くのはよせ」 「オレ、ウタちゃんと一緒にいたいって言ったけど、そんなことしたら、絶交だからね」 幽霊に絶交と言われても、これ以上何の縁が切れるんだと突っ込みたいところだったが、それを飲み込む。 「送り火まで、まだ少しあるよな?」 「……うん」 「それまでは、一緒にいてもいいんだろ」 その分だけ別れが辛くなるだろうが、それでも俺はこの短い夏の盆をキンと過ごしたい。 祭りの終わりが近づいているのか、会場の提灯が一つ、また一つと消えていく。それに従って俺とキンの輪郭も朧気になり、まるで夜に融けていくようだった。 去年まではキンの荷物持ちをさせられて、袋一杯のガラクタを抱えていたはずなのに、今年は冷めきった焼きそばと小さく鈴の音を立てている赤笛が手元にあるだけだという事実に、疼くような胸の痛みを俺は感じている。 「うん。あと少し、傍にいさせて」 消え入りそうなキンの声がして、暗闇がさざ波のように押し寄せる。俺たちは触れられない手を重ね合わせ、祈るように目を閉じた。 〈了〉 |