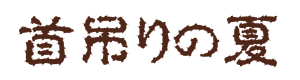
「小芝居ユニット/Funny Butterflies.」の
BLエチュード作品『首吊りの夏』をノベライズ化いたしました。
際どいラインなのですが、一応15禁作品とさせていただいております。
15歳未満の方、BLが苦手、という方は閲覧をお控えいただきますようお願いいたします。
このページは全4回のうち2話目です。
↓
↓
↓
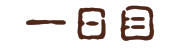
|
一日目。僕と上沼は〈上沼雑貨店〉から徒歩八分のところにある海岸に来ていた。人の入りはそれなりで、点々とビーチパラソルが白い砂浜に立っている。 「……上沼」 海の家の片隅に座り、僕はどんよりとした気持ちでフルーツジュースに夢中になっている上沼に声をかける。 「ひゃんひゃ?」 「ストローから口をはなせ」 「おっと。んで?」 「どうして僕らはこんな所にいるんだ」 「そりゃ、夏を楽しむために」 「阿呆くさい、帰る」 星形サングラスを頭に乗せたヤツと海辺で隣り合わせることほど馬鹿らしいことはない。 「まー、そう言うなよ。ほらナンパし放題じゃん、海なら」 「悪いけど、女の子には困ってないから」 「ええー、興味ねーってか?」 「言葉が難しかった? 「足りてる」ってことだよ」 僕が馬鹿にしたように微笑むと、上沼はむせて、ふがっふぁ、という奇声を上げた。 「ごほっ、え? マジで? なにお前いつの間にチェリー卒業しちゃってんの?」 「かれこれ四年ほど前に」 「中二とか俺と一緒じゃん! さっぱり気づかなかった!」 「ほら僕、世間知らずでお上品そうに見えるから、年上のお姉さんたちにほっとかれないって言うか」 「悪人だな」 「そうかもね。僕、はじめてなんです……って毎回言ってるし」 「お前……ホント、イイ性格してるよ」 どうも、と言って僕は上沼に押しつけられたブルーハワイのかき氷を口に含む。 夏期講習の帰り際に拉致されたため、僕はビーチで学生服という苦行のような格好を強いられている。半袖のワイシャツはまだしも直射日光で黒のスラックスが火傷するかと思うくらい熱くなってきたので、僕は靴下を脱いで、スラックスを六分丈くらいまで折り上げた。 「全然筋肉ないな、お前」 僕の足を見て、上沼が言う。 「まぁ、運動しないからね。常に省エネモード」 「その溜めたエネルギーどうすんだよ」 「来世に繰り越し、かな」 「契約内容はよく確認した方がいいぞ?」 「……そうだね」 海上からビーチに向かって、大きく風が吹いた。それに運ばれて、むっとするような籠もった熱と、潮の香りが僕らに襲いかかる。 「すごく……べたべたする」 まとわりついた風が振り払えるわけもないのに、僕は頬を手の甲で拭った。 「あ、思い出した。上沼勇次郎クンのトリビア」 「残念ながら当番組は終了となりました」 「投稿させろよ! 賞金くれよ!」 「じゃあ代わりにブルーハワイ溶けたヤツで」 話しているうちにほとんど溶けてしまったかき氷を上沼に押しつける。 「で、なんなのさ」 僕は、シロップが薄まっただけの液体と化したかき氷を律儀に飲み干した上沼へ問いかけた。 「……海の匂いってさ、潮の香りとか言うじゃん?」 「ああ」 「でも、あれは生き物の死骸の匂いなんだっつー話」 ホントかどうかは知らねぇけど、と上沼は笑った。それから水平線の向こうを見て、 ――お前が首吊ったあとも、同じ匂いすんのかな。 そう、言った。 〈続く〉 |