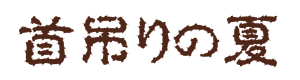
「小芝居ユニット/Funny Butterflies.」の
BLエチュード作品『首吊りの夏』をノベライズ化いたしました。
『首吊りの夏』は2012年の6月末から8月上旬にかけて彩の国某所のカラオケ店の片隅で開催された、
全4回のエチュード(即興芝居)であり、わたくし二山は記録係兼参加者として関わらせていただきました。
その後、「Funny Butterflies.」の
内容を整理し、シーンをつけ足した形でノベライズさせていただいております。
際どいラインなのですが、一応15禁作品とさせていただいております。
バイオレンスやBLが苦手、という方は閲覧をお控えいただきますようお願いいたします。
このページは全4回のうち1話目です。
↓
↓
↓

|
夏の到来とともに劣等生である僕にはいくばくかの時間の制約が設けられ、世界の理を把握するための特別な呪文を教授される。 「x=yとなるためには式の展開が必要になり……」 つまりは数学の夏期講習である。イマドキ、男子は理系強くないと食いっぱぐれるとか言われてもね。それすらも時代遅れで、なにしてもご飯が食べられない世の中じゃないですかという反論は不可、らしい。世の中、捨てたもんじゃない、とか。そういうことを言って、センセーたちは僕らを元気づけてくれる。……あんまりワカモンの生きる気力を削がないようにしないと飼い殺しできないっていうのがホンネか。ただでさえ年金のノルマがっつり上がっちゃってるし。一ヶ月単位で僕らが納めなきゃいけない年金がだいたい千円ずつ上乗せされてるのとか知ったらもう生きていくだけ無駄な気がする。 先生が呪文の詠唱に勤しむなか、僕のノートには呪文の代わりにいびつな丸が一つ書かれたきりだ。窓の外を見ると、田圃と舗装されていない道が延々と続いていて、夏の空は黒ずんだ青色をしていた。僕はノートのいびつな丸の中を塗りつぶす。これが僕の行く場所だ。世界にさよならを言おう。抜け穴なんだ、これは。そう、僕はこの世界からオサラバしてやるのだ。 ――蝉の声がいやに煩い。 世界からオサラバするとなると、なにが必要だろうか。学校と変わらず、蝉の鳴く帰り道を歩きながら僕は考える。まずどうやってオサラバするか。いくらさっくり死ねるとしても現代においてギロチンはなかなか手に入らないだろうし、切腹は介錯が必要だし。他人に迷惑かけるような轢死もよくないし。やっぱ、首吊りかなぁ。それならロープと天井のある部屋さえあれば済むし。ロープならそんなに高価じゃないだろう。僕は滅多に列車の通らない線路沿いの小道を歩いて、〈上沼雑貨店〉の前まで来た。たてつけの悪いガラスの引き戸を手で開けると 「いらはーい」 と間抜けな声がした。とても客に対する態度とは思えない。 「あ? 美鶴? めずらしーな、ウチ来るなんてよ」 「君も珍しいね。大人しく店番なんて」 〈上沼雑貨店〉二代目になるかもしれない男・上沼勇次郎(カミヌマ・ユウジロウ)が小さなラジオのスイッチを止め、こちらを見る。 「俺は遊ぶ金欲しさ」 確かに、こんな田舎で脱色しきった白髪頭じゃ、実家以外雇ってくれるところはなさそうだ。それにピアスの数が尋常じゃないし。 「僕は野暮用」 ふーん? と興味があるんだかないんだかわからない調子で上沼が相づちを打ってくる。 「で? その野暮用になにをお探しで?」 売り物なんだか、ガラクタなんだかわからないような品々を手で示しながら上沼が言った。 「ええと、ロープある?」 「ロープ? あれか、エロ本の整理でもすんのか。ならカモフラ用に健全な雑誌も一緒にどうよ?」 上沼がレジカウンターの横にあるラックから一冊抜き取ってこちらに差し出してくる。 「よくわからない妄想を一方的にして押し売りをするんじゃない。それからその雑誌、一月号って書いてあるのバレバレだからな」 「細けぇこたぁいいんだよ、たかが半年ちょい前だからってそう世の中変わるもんじゃなし」 「半年もあれば移り変わるもんじゃないのか、世の中」 「トップの政治家の名前が今と違ってることになんの意味があるってーの?」 まるで世捨て人のような発言に僕はためらいながら言った。 「……上沼」 「ん? なんだ?」 「それ、漫画雑誌」 夏だというのに上沼雑貨店にサムい空気が流れた。 「……えー、まぁ、アレだな。半年くらいじゃ人気作家の連載は一つのバトルの勝敗がつくかつかないかくらいじゃねーの!」 「人気ない作家は打ち切られてる頃合いだけどな」 「こ、細けぇこたぁいいんだよ!」 あからさまに狼狽しながら上沼が叫ぶ。 「で。ロープ、あるのか、ないのか」 「このマイペースさんぶっ飛ばしてぇ……」 拳を固めかける上沼をどうどうといなしながら僕は言う。 「空気は読めるけどシカトするタイプです」 「なお悪いわ! ……ったくよー、ええと」 上沼はレジカウンターから立ち上がって、店の奥にある引き出しだらけの棚を物色し始める。あれでもないこれでもないと散らかすさまは某お腹に四次元空間を持った青いたぬき……じゃなかった、ネコ型ロボットよろしくな感じである。 「って、ちょっと待て上沼」 「あ? んだよ、せっかく俺が手ずから探してやってんのに」 「いやどう考えてもその棚は違う」 「だって、ロープだろ? エロ本縛るんじゃないっつーなら、もうこのコーナーしか考えらんないじゃん」 まるで意味が分からないとでも言いたげに上沼は「大人の玩具」コーナーの棚を漁り続けている。 「……エロ本縛るだのなんだのの発想が出てくるなら、普通に考えて「梱包用」とか思わないのか」 僕がぼそっと突っ込むと、上沼の動きがぴたりと止まった。そして 「ベ、別ニ、コレシカ思イツカナカッタ訳ジャナインダカラネ!」 カタコトな言葉を口にしながらこちらを振り返る。 「いやさっき「このコーナーしか考えらんないじゃん」とか言ってたよ君」 「ぎゃああああ!プレイバックしちゃいやー!」 両耳を塞ぐような仕草をしながら、上沼は別の棚に移動する。そしてガムテープやビニール紐の中から一束のロープを発見したようだった。 「これか?」 予想以上に貧弱なつくりのそれを上沼から受け取り、僕は試しに軽く引っ張った。切れた。 「ああー!ちょ、美鶴、なにしてくれちゃってんの!」 「いや、不良品つかまされないようにと思って確認を」 千切れたロープをもう一度結び直して、上沼にパスする。 「やっぱり街行った方が早いかな」 「悪かったな、ボロい雑貨店で。つーか使用用途不明じゃどんなロープがお望みなのかわかんねーだろ」 ああ、こりゃもうだめだ、とぶつくさ言いながら上沼がロープをいじり回す。僕は一瞬答えに窮して、それから 「わっかを作って少し余るくらいの長さで、五七、八キロくらいの重さに耐えれそうなヤツ、かな」 そう返した。すると、 「なんだ、人でも吊るのか?」 当然のように上沼は言ってきた。僕は平静を装って尋ねる。 「……どうして」 「わっか作って余るっつーことはロープをなんかに引っかけて引っ張るなり吊すなりするんだろ? で、普通荷物の重さってのは端数は言わねぇ。五〇キロくらいとか、せいぜい言っても五五キロとか五の倍数だな。それがわざわざ端数まで言ってんだから物体の重さがその種類の中でも個別に違うことが予想される。んで、そんな条件に当てはまるもんで五七、八キロつったら人間かと思っただけ」 そう言いながらロープを脇へやり、上沼がこちらへ近づいてきた。なんとなく嫌な雰囲気を感じて後ずさると、強引に手首を掴まれた。 「痩せ型、俺からマイナス五センチくらいだから一六九くらいか」 上沼がなにを言ってるのか僕にはよくわからず、戸惑っていると身体が急にすくい上げられた。 「正味、五七、八キロ」 「上沼? なにしてるんだよ、降ろせ」 他人に抱え上げられるなんてごめんだ。僕がもがいていると、耳元で 「……なんだ。自分を吊るのか、お前」 ぞっとするほど無感情で低い声がした。ごまかしはいっさい許されないような、冷え冷えとした声。僕は上沼の顔を見ないまま、そうだよ、この世界からオサラバするんだ、と小さく言った。 「もう自分は死んじゃった方がいい、とか、そういうこと?」 「ッ、……うるさいな、関係ないだろ」 僕はむりやり上沼の腕から抜け出て、着地する。そして引き戸を開けようとした。 「俺になんも口止めしなくていいワケー?」 先ほどとは違う、いつも通りの間抜けな声が僕の背中にかけられる。 「口止め?」 振り返って僕は尋ねた。 「そ。だって俺、口軽いからさ。児童相談所とか、教育委員会とか、自殺一一〇番とか、あるいはお前のゴリョーシンとか、口うるさいところにうっかり話しちゃうかも」 「それは大したうっかりだね。……なにをしろって言うの?」 僕が睨みつけると、どこ吹く風とでもいうように上沼はにいっと口の端をつり上げた。 「壮行会への出席を義務づける」 「は?」 「注文してやるよ、ロープ。ただ、こんな辺鄙な場所だから三日はかかる。だからその三日間、俺がお前のために壮行会してやるって言ってんの。盛大に祝ってやろうじゃねぇの。お前の旅立ちを」 「……うさんくさい」 「でもお前にゃ、乗る以外の選択肢ねーけどな?」 あは、と妙に可愛い子ぶった仕草で上沼は笑い、僕の小指を無理に曲げて指切りげんまんをさせた。 〈続く〉 |