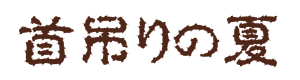
「小芝居ユニット/Funny Butterflies.」の
BLエチュード作品『首吊りの夏』をノベライズ化いたしました。
際どいラインなのですが、一応15禁作品とさせていただいております。
この最終話に関しましてはバイオレンスの要素を含めておりますので、
暴力・BLなどに耐性のない方はご注意をお願いいたします。
このページは全4回の最終話です。
↓
↓
↓
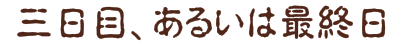
|
三日目、あるいは最終日。昨晩、遅くまで上沼に連れ回されたせいで夏期講習の宿題がやれずじまいになってしまった。そのせいで僕は数学の準備室でお説教を受ける羽目になっている。わざわざ準備室に呼び出すなんてどんな人目をはばかる説教ってなんだ、って思うかもしれないけど、僕の高校の数学教師は、まぁ若めの美人であることだけは追記しておく。つまりそういうことだ。 お説教(という名のいちゃいちゃタイム)が長引いてしまったせいで腕時計を確認すると、もう午後になっていた。さすがにこのまま上沼の家を訪れるのも気が引けたので、一度家に帰ろうと校門を出ると、 「よう」 上沼がアイスバー片手に立っていた。 「……逃げたかと思った」 「どうして僕が逃げる必要があるんだよ」 「なんかあった?」 「別に大したことはなにも。宿題やるの忘れて、お説教食らってた」 「キスマークつけられるような説教か」 「あ、残ってる?」 反射的に一つだけ開けていたワイシャツの釦をしめる。 「いーや。カマかけただけ。ったく、どっちが食らってるんだか」 「なんだ。まんまと乗っちゃったよ」 「つくづく腹黒なのか天然なのかわっかんねーヤツ」 上沼はそう言ってから小さくなったアイスバーを口にくわえ、横に駐輪していた自転車のスタンドを外した。 「ん」 「後ろ、乗っていいの?」 「ひゃんひょひゃひぇに……あ」 横着をしてアイスバーをくわえたまま喋った上沼の口から、最後のひとかけらが道に墜落した。 「あ……あぁ……! ここまで苦楽を共にした戦友が無惨な姿に!」 「具体的には」 「約一〇分」 「一期一会と思いなよ……出会いがあるなら、別れもあるさ」 僕は上沼の肩を叩いて、自転車の荷台に座った。 「急に雲が出てきたな。ウチまで持つかねぇ」 上沼がぎいこ、ぎいこ、と自転車をこぎながら言う。僕もつられて前方を見ると、入道雲が見上げなければいけないほど大きく成長しており、心なしか遠くから雷の音が近づいてきている。 「遠雷だ」 「げ。こんなだだっ広いとこに落ちるつったら、俺たちイイ標的じゃねーか! 急ぐぞ!」 急に自転車のスピードが上がって、とっさに僕は上沼にしがみついた。 「ぶふぐわっ」 「ごめん、上沼。っていうかそれ何語? モンゴル相撲を描くための水彩絵の具を人気アニメ風に略したギャグ?」 「ブフ・グワッシュの略じゃねー! マニアックなツッコミさせんな! あと原語バラバラだからコラボできねーし! 一繋がりの文章にならねーっつの! あとイマドキではガッシュだかんな! グワッシュとか古語だからな!」 「僕もまだまだだな……」 「そういうことじゃなくてだな? 俺ね、チョーくすぐったがりなの」 「うん」 それはなんとなくわかっていたけれど、あえて気づかないふりをしてた。 「で、中途半端に腰とか持たれるともうなんていうかうっちゃりかましたくなるくらい耐えらんないの。OK?」 「善処するよ」 霧のような雨が降り始め、一分もしないうちに雨粒は大きくなって土砂降りに変わった。上沼はさらに自転車の速度を上げ、僕はもう一度、上沼にしがみつくことになった。 「ぶひゃらー!」 あ、これおもしろいや。上沼の身体が小刻みに震えてる。 「ッ、美鶴! テメェその辺の田圃に放り込むぞコラァー!」 なんとか落雷の危機を乗り越え、〈上沼雑貨店〉にたどり着いた僕らだが、二匹の濡れネズミになることは回避できなかった。 「もーダメ。明後日筋肉痛だわ……」 店舗内にフラフラと二、三歩入ったところで、びしょ濡れのまま上沼が膝をついた。 「老化早いね。同い年なのに」 僕も水滴のせいで額に貼りつく髪の毛を何度か払って、お邪魔する。 「誰かさんのせいでいらん腹筋使ったせいだっつーの」 「不可抗力だよ。あのスピードで掴まってなかったら振り落とされるって」 上沼は「準備中」の札がかかっていることを確認してから、店の入り口に鍵をかける。 「ったく。……さすがに夏とはいえ、このままじゃバカの道まっしぐらだな」 「別名・夏風邪一週間寝込みコース、オプションで腹筋、大腿筋の筋肉痛セットがオススメです」 「ばーか。バカの道っつったら夏期講習なんざ受ける羽目になってるお前の得意分野だろうが。タオルと着替え用意してやっからとっとと風呂場行け、ばーか」 からかいすぎたせいか、上沼の口の悪さが当社比三〇%くらい上がっている気がする。それと同時にボキャ貧のレベルもぐいぐい上昇中だ。その割にはいそいそとタオルだのなんだの準備していて、本当に上沼は面倒見のいいヤツである。 「じゃ、お言葉に甘えるよ」 「おらよ」 着替え一式とバスタオルを上沼から受け取り、僕は上沼家の風呂場へ向かうことになった。 雨足が強まっている気がする。雷もひっきりなしに近くへ落ちているようだった。僕は風呂から上がって、昨日浴衣をむりやり着せられた畳の部屋に顔を出す。すると上沼は新しいTシャツと短パンに着替え終わって、頭に工事現場のあんちゃんよろしくタオルを巻いて寝っ転がっていた。 「お先に」 「おう。って、あれ、俺タンクトップ渡してなかったっけ?」 上半身にバスタオルしかかけていない僕に、上沼が怪訝そうな声を出す。 「いや、あるけど。すぐ着るとまた汗がつくから」 さすがにズボンを履いておく良識はあるよ、と笑いながら言うと、ったりめーだ、と無愛想な返事をされた。 「上沼は? お風呂入らないの?」 「着替えちまったし、なんかめんどくなってきた」 「そっか、悪いね」 上沼に背を向けて、バスタオルを頭からかぶったままぼうっと窓の外の空を見上げる。 「雨、すごいなぁ」 黒雲の隙間から時折、なにかの誕生を告げるように稲光が閃く。衣擦れの音がしたので振り向こうとすると、前を向かされたまま、がしがしと頭を拭かれる。 「なんのための風呂だと思ってんだ」 「はは、ペットシッターみたいだね、君」 「ホントに手のかかるペット様だこって」 僕がされるがままになっていると、ふいにバスタオルが視界から消え、むき出しにしていた肩に上沼の手が触れた。 「……壮行会、楽しかったか?」 耳元で聞こえたその声は、いつもの上沼の声じゃなかった。僕の首吊り計画を否定も肯定もせずに確認してきた、僕が恐ろしさを感じた低い声。 窓の外で稲妻が凄絶な光を放ち、僕は怯む。なにかが僕の首に絡んでいる。二拍ほど置いて地響きがした。僕は上沼の顔を見ようとする。地響きは収まらない。僕は引き倒され、上沼に伸しかかられていた。上沼の手にはロープが握られている。それは僕の首を一周し、圧迫していた。 「か、上沼……ッ、なんで」 上沼の手首を掴み、僕はロープを解こうとする。 「なんでって、おかしなこと訊くなよ。お前、死にたいんだろ? 首を吊りたかったんだろ? この通り、念願のロープが来たからな。俺が吊ってやってんだよ」 彼の瞳は、僕が首吊りを思い立った時にノートへ描いた穴のように真っ黒だった。僕は首を横に振る。違う。僕が望んでいることは、違うんだ。でもなにか違うのか、わからない。声も出せずに僕はただもがくしかできない。 「いいか、美鶴。上沼勇次郎クンのトリビアだ」 海岸での軽口とまったく同じ調子で、上沼は得意げに言う。 「人間が、首を吊って死ねるまでの時間は、平均十三分だ。だからお前は耐えなきゃいけねーの。十三分間。意識はいつまであるか知らねぇけど」 ロープがさらにきつく首に食い込む。頭の奥で真っ白な光が何度も何度も何度も明滅する。抵抗する腕に力が入らない。痛みのあまりに反射的な涙が出て、視界がぼやけていく。 世界からオサラバだなんて虫が良すぎる言葉だったんだと僕は気づく。人間はそんな簡単に消えられる生き物じゃなかった。僕らは銀河鉄道に乗せてもらえないし、偏屈な渡し守に小舟で運んでもらえるワケでもない。 ――ふいに、自分の呼吸が楽になっていることに気づく。上沼の手は、震えていた。そして、できるわけねーだろ、こんなこと、と彼は呟いた。 「……なぁ、わかるか。自分が、どんだけ浅はかなこと考えてたのか」 むせている僕の頬に、熱い雫が落ちてくる。いつだって余裕の笑みばかり浮かべていた上沼が、泣いている。 「気づかねぇならお前の言葉で言ってやる。「阿呆」だ。お前、マジで阿呆だっつーの」 「……うん」 世界から抜け出すために必要なものは、銀貨じゃない、捧げ物じゃない、祈りじゃない。 「オサラバとか抜かして別れられるほど、世界は慈悲深くねーんだよ」 ようやく僕は知る。 「君は、僕に慈悲をくれるの?」 「俺は仏様じゃねーんだよ。……でも、お前がお前を殺すってなら。俺がこの場で殺してやる。絶対にお前に人殺しはさせない」 「つまり?」 「お前は善良なまま死ねってこと」 「……よくわからないよ」 「バカなお前にゃ、一生わからなくていーんだよ」 「うん」 世界から抜け出すことは、世界にさよらならを言うことは、凡人の僕にはできない。六五八円のロープで楽に逝けるほど、死の道への路銀は安くなかった。 世界から抜け出る方法はただ一つ。それはとてもシンプルな答えなのだ。その運命がやってくるまで、僕らは生きていくしかないということ。それだけだった。 僕は「ごめん」と言おうとして、けれど、それはなにかが違うような気がして、 「……ありがとう」 そう言って、僕は上沼をそっと抱きしめた。 どのくらいそうしていただろう。雨はゆっくりと遠ざかりはじめていた。雷鳴はもう聞こえない。 上沼を抱きしめたまま目を伏せた先に、部屋の隅に置かれたロープがあった。首吊りのことを考える僕は、きっと勇次郎があのロープで殺してくれたんだと思う。首吊りの夏は、雷鳴とともに過ぎ去ったのだ。これからは呼吸することを考えればいい。リスタート・サマー。勇次郎が隣にいる夏が、始まる。 ――蝉の声が心地良い。 〈了〉 |